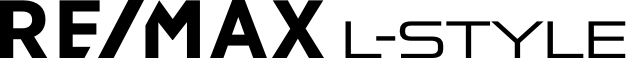不動産を“共有名義”で相続すると危ない!? ── 相続トラブルを回避する分け方とは
相続で最もトラブルになりやすい財産、それは「不動産」です。
特に兄弟姉妹で相続する場合、よくあるのが「とりあえず共有にしておこう」という選択。
でも、この“共有”という選択肢、実は後々に多くの問題を引き起こす火種になるのです。
本記事では、「なぜ共有は危険なのか?」から始まり、「ではどう分ければよかったのか?」という4つの方法、そしてそれぞれのメリット・デメリットまで、徹底的に解説していきたいと思います。
目次
なぜ“共有名義”は危険なのか?
共有名義とは、相続人全員で1つの不動産を持つ状態のことです。
一見、平等でスマートな分け方に思えるかもしれませんが、以下のようなリスクがあります。
- 売却や建て替えができない:共有者全員の同意が必要。1人でも反対すれば不可能。
- 管理が難しい:修繕や固定資産税の支払いなどで揉めやすい。
- 代替わりでさらに複雑に:共有者の死亡により、持ち分が次世代に分散され“分割不能地獄”に陥ることも。
- 疎遠な親族との関係悪化:連絡がつかず、物件が放置状態に。
つまり、共有は“とりあえずの先送り”に過ぎず、のちに大きな問題へと発展しかねないのです。
実際に私たちの元に来る相談でも、この共有名義が故の問題も少なくないのです。
『私たちはもう処分したいと思っているのですが、兄が売却することに反対していまして・・』
『兄弟で相続した家に弟が住んでいるのですが、このまま私がもし亡くなったら子どもたちの代で困らないか心配なんです。』
共有名義の問題点は、兄弟同士だけの問題ではなく、兄弟それぞれの配偶者、そしてこどもの問題にも発展する火種にもなっていくのです。
相続不動産の分け方──4つの方法
では、不動産はどう分けるのが正解なのでしょうか?
① 現物分割
実際の不動産をそのまま物理的に分ける方法。
たとえば、兄が自宅を、妹が別の土地を…といった分け方です。
- 【メリット】具体的でわかりやすい
- 【デメリット】不動産の評価が異なると不公平感が出やすい
② 代償分割
特定の相続人が不動産を引き継ぎ、その代わりに他の相続人に金銭を支払う方法です。
- 【メリット】物件を売却せずに残せる
- 【デメリット】代償金の準備が必要(ローン活用など)
③ 換価分割
不動産を売却して、その売却代金を分ける方法です。
- 【メリット】公平性が高い/現金で分けやすい
- 【デメリット】タイミングによっては希望価格で売れない可能性も
④ 共有(できれば避けたい)
相続人全員が持分を持つ状態のまま保有する方法。
- 【メリット】一時的な回避策にはなる
- 【デメリット】前述の通り、長期的に見て問題が大きい
これらの4つの分け方のメリット、デメリットを一つ一つ掘り下げていきます。
現物分割(不動産ごとに名義を分ける)
✅ 不動産ごとに名義を分けるメリット(現物分割)
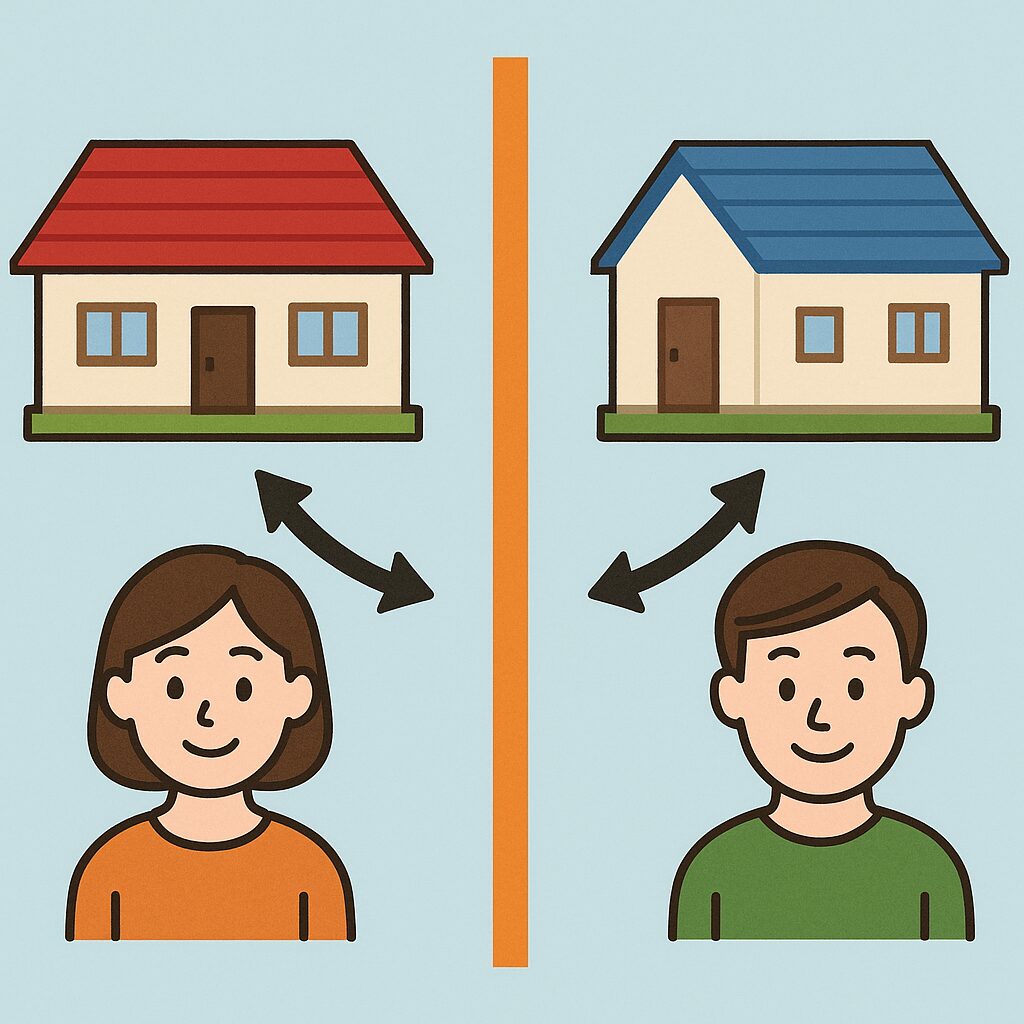
① それぞれの不動産を単独で管理・活用できる
「誰がどの物件を持つか」が明確になるので、管理・売却・賃貸などがスムーズになります。
共有名義のように「全員の同意」が不要になるのも大きなメリットです。
② 使いたい人がその不動産を相続できる
例えば、長男が実家に住み続けたい、次男は投資用物件を相続したいなど希望に沿った分け方が可能になります。
仕事や収入が安定している長男には、守ってほしい土地、不動産を。
まだ仕事や収入が確立できていない次男には、収入の足しになるような不動産を相続させる、このような継承も可能になります。
名義人が自由に相続した不動産が使えるのもメリットの一つです。
③ 次世代へのトラブルを減らせる
不動産を単独所有にしておくことで、将来的な名義人の分散を防げます。
単独名義にさえしておけば、その不動産を相続するのは自分の配偶者及びこどもに限定されます。
その自分の相続の時も、遺言書等で「誰に」「どの不動産を」相続させるか決めておくだけで、将来的な名義人の分散を防ぐことができ、共有名義が原因の「売りたくても売れない問題」が回避できることになるのです。
④ 現物を維持したまま分割できる
不動産を現金化せず、資産として「形あるまま」残せます。
残したい資産を残したい人に、これができるのは現物分割だからこそです。
❌ 不動産ごとに名義を分けるデメリット
① 不動産ごとの評価に差があると不公平感が生まれる
都市部と地方、築浅と築古などで評価額に大きな差が出ることがあります。
遺産総額のバランスを取るのが難しい → つまり揉める原因にもなりやすかったりします。
なので、どのような分け方が公平なのか、そのジャッジは第三者(税理士や不動産鑑定士、不動産会社などの専門家)の介入がないと難しいと言わざるを得ません。
② 分け方に工夫が必要(適当に分けると損)
評価額だけでなく、収益性・維持費・将来性なども加味しないとトラブルになります。
例:「Aさんは価値が高いが空き家の物件、Bさんは古くても家賃収入がある物件」
どちらが有利で、どちらがリスクが高いなどの見極めも重要になってきます。
③ 不動産が少ないと分けられない
この方法はそもそも複数の不動産がある場合しか選べません。
1物件しかない場合はこの方法は取ることもできず、選択肢の一つにもなり得ないかもしれません。
④ 固定資産税のバランスが崩れることも
表面上の評価は同じでも、税負担や修繕の手間が片方に偏ることがあります。
数字だけのバランスでは不公平感が出ることもしばしば。
やはり、専門家の意見、アドバイスを受けることを推奨いたします。
代償分割(1人が相続し、他の相続人にお金を支払う)

✅ 代償分割のメリット
① 不動産を売らずに残すことができる
実家など思い出の詰まった不動産を手放さずに相続できます。
同居していた相続人が引き続き住むことも可能に。
継ぎたい人、継がせたい人に引き継ぐことも可能になるのです。
② 不動産の共有名義を避けられる
相続人全員で共有せずに、単独名義にできるので、管理・売却・活用がしやすくなります。
誰か一人の名義にし、その対価として代償金を支払うというのがこのやり方なので、不動産の共有名義にする必要がないのです。
③ 他の相続人には“現金”で公平に分配できる
不動産の相続と代償金で、バランスの取れた分割が実現になります。
換価分割と違って不動産を保持しつつも、公平な相続ができるやり方でもあるのです。
④ 早期に相続を完了しやすい
全員の共有や売却などの煩雑な調整を避けて、一括処理できることも多いのがメリットです。
不動産を取得するものとその代わりの対価(現金や有価証券など、金額が決まっている資産で代替)をもらう人、公平な配分がしやすいのも特徴です。
❌ 代償分割のデメリット
① 代償金を用意できないと成立しない
不動産を取得する相続人に十分な資金力が必要になります。
ローンを組む場合もあるが、その場合はそもそも審査が必要になる場合もあり、それに加え返済リスクが発生します。
潤沢な現預金があれば、長男のAさんは不動産と現金一部、次男Bさん、長女Cさんには現預金で同じ資産配分になるように受け取るという形も実現可能になります。
② 不動産の評価に対して不満が出やすい
「本当にそんなに価値あるの?」「もっと払ってよ!」と代償金の金額をめぐって揉めやすい状況は避けることができません。
路線価をもとにするのか、固定資産税評価額なのか、実勢価格なのかなど評価基準が複数あり、それぞれの合意が必要になってきます。
ですので、ここでも専門家や第三者の意見が介入することになるかもしれませんね。
③ 税務処理がやや複雑になる
代償金を支払った相続人の申告は、少し煩雑になります。
ここに関しては税理士の先生に意見をもらいながら進めていくのがいいでしょう。
代償金の額によっては、支払った側・受け取った側で贈与税扱いになるケースもあります(形式が不適切な場合や相続税の申告内容と乖離があった場合なども)。
④ 相続後も関係がこじれる可能性
相続時に全額一時金で支払えない場合、代償金を巡る
「払う・払わない」
「時期・分割払い可否」
などで、信頼関係が損なわれることもあります。
その場しのぎでの約束で代償金の話をしてはいけませんね。
換価分割(売却して現金で分ける)

✅ 売却して現金で分けるメリット(換価分割)
① 分けやすい・揉めにくい
現金は割り切れる!→ なので、相続人ごとに明確に金額が算定でき「不公平感」が出にくくなります。
そのため遺産分割協議がスムーズになりやすいのです。
現金で受け取ることにより、相続人それぞれの希望するお金の使い方が実現できます。
売却して得たお金で再度自分好みの不動産を購入するのもよし、現金でそのまま保管しておくのもよしで円満解決になりやすい手法です。
② 管理の手間がなくなる
不動産を保有しなくなった分、その不動産の管理・固定資産税の負担がなくなります。
将来の相続人(孫世代など)に「共有名義がどんどん増える」問題も引き継がずに済むことになります。
③ 不動産を現金化して他の用途に使える
現金に換金するので、医療・介護費、生活費などにも充てやすくなります。
代償金の支払いなども、売却益からまかなえることがあります。
引き継いでもらいたい不動産を長男に遺すために、他の不動産を売却して代償金に充当する、このようなケースで使う手法です。
④ 節税・申告がしやすくなる
所得税や譲渡所得税が発生するが、処理が一度で済みます。
現金になればその後の相続税納税も行いやすくなるため、現預金が不足している相続では多くの活用方法があるでしょう。
❌売却して現金で分けるデメリット
① 想定通りの金額で売れないリスク
売却額が相場より低くなることもあります。
売却時期・タイミングに左右され、時には思っていた金額より大幅に下がった金額で売却することにもなりかねません。
② 思い出の詰まった不動産が手元に残らない
売却して不動産そのものがなくなってしまうため、「実家を残したかった」「誰かが住みたかった」など感情面の反発が起きやすいこともあります。
特に地方や田舎では「本家を守る」意識が強い人も多く、「何も売却しなくてもいいんじゃ」という意見も出やすいのもたしかです。
③ 売却に手間と時間がかかる
不動産会社に仲介依頼 → 内見 → 成約 → 決済と、手続きが長いため、急ぎの現金化ができないケースも出てきます。
特に希望価格で売りたい場合には、時間を要してしまうことも多々あり、価格調整も大切なファクターとなります。
④ 譲渡所得税がかかるケースもある
被相続人の取得価格によっては「譲渡所得」が発生する可能性あります。
そのあたりも考慮した価格設定が必要になります。
ただし「取得費加算の特例」や「3,000万円控除」などの制度で軽減可能な場合も。
💡こんなときにおすすめ
◦相続人の間で利用希望者がいない
◦遺産のバランスが取りづらい
◦現金化してそれぞれ自由に使いたい
◦不動産の管理が煩わしい・遠方にある
共有(共有名義で保有)

✅ 共有名義にするメリット
① 手間をかけずに“とりあえず”相続できる
他の相続方法(売却や代償分割)と比べて、話し合いがまとまらないときに「保留」的に使いやすいのがこの方法です。
登記も簡単(相続人全員の持分割合を決めて名義変更するだけ)、手続きも簡単。
遺産分割協議がまとまり切らないケースで最終手段で利用することもあります。
② 不動産を手放さずに済む
売却しないので、思い出の詰まった実家などを残すことができます。
将来的に使う・住む可能性がある家族がいればキープできるというメリットがあり、やはり保留的な意味合いで使うことが多い手法です。
③ 不公平感を軽減しやすい
「誰か1人だけが得をした」と思われづらいのがこの方法です。
財産評価で差がつきにくいときに選ばれやすい方法。
ただ、安易に税理士の先生が勧めてきたときには注意が必要ですが、家族間の話し合いがなかなか進まず、進展が見られない場合などでは仕方がない選択かもしれません。
❌ 共有名義にするデメリット
① 全員の同意がないと売却や賃貸ができない
共有者の1人でも反対すれば、売却・貸出はできません。
将来的に「誰かが住み続けていて、他の人はお金だけ欲しい」という状況が揉め事の元になることも。
② 固定資産税などの支払いが不公平になりやすい
実際に使っている人と払っている人が別になりがちです。
管理費用や修繕費の負担分担が曖昧になり、そのことが要因で家族間のもめごとになるケースも。
③ 次世代にいくと“名義人が増えすぎる”
リスク共有者が亡くなると、その相続人にさらに分割されます → すると、名義人が10人以上になることも。
そうなれば、売却・処分の同意がますます難しくなり。意見がまとまらずそのまま塩漬けになるケースも。
④ 持分だけの売却は現実的に困難
自分の共有持分だけを売ることは理論上可能だが、買い手はほとんどいません。
業者買取で安く買い取られ、他の共有者も苦労することになります。
揉めたときは最悪「共有物分割請求訴訟」に発展することも想定しておかなければなりません。
節税にも関わる「分け方」と「引き継ぎ方」
実は不動産の分け方は、単なる“話し合い”で済む問題ではありません。
相続税には「小規模宅地の特例」や「債務控除」など、 “誰が”相続するかによって適用可否が変わる制度があるのです。
- 自宅を「同居していた子」が引き継げば、評価額を80%減できる(特例あり)
- 共有にしてしまうとこの特例が使えないこともある
- 売却予定なら「換価分割」が最適なケースも
相続は「節税」だけでなく、「遺族の将来の暮らし方」にも直結する問題であり、単なる分割ではなく、「その後どうなるか?」まで考えた選択が必要です。
💡「債務控除」とは?
相続税は「相続財産の総額」から「債務(=借金)」や「葬式費用」などを差し引いた“正味の遺産額”に対してかかります。
たとえば…
- 不動産や預金などのプラスの財産:1億円
- 住宅ローンなどの債務:▲3000万円
- 葬式費用:▲200万円
➡ 正味の遺産額:6700万円
つまり、借金があればあるほど、課税対象の遺産額は小さくなるというわけですが、債務控除は「相続人が負債も引き継ぐ場合」にのみ適用されるので、
「不動産だけもらって、ローンは引き継ぎたくない」といった分け方をしてしまうと、控除が使えない場合もあります。
たとえば…
不動産(1億円)を兄がもらい、ローン(3000万円)を弟が負担
➡ この場合、兄の相続税評価額は1億円まるまるになってしまう可能性があります
そのため、
✅ 不動産+債務をセットで同一人が引き継ぐ
→ 債務控除が効き、相続税評価額を下げられる!
という「引き継ぎ方の設計」が大事になるわけなんです。
相続は“とりあえず共有”で済ませる時代じゃない
- 不動産相続で“共有”を選ぶと、将来的なリスクが大きすぎる
- 現物/代償/換価分割、それぞれに適したケースがある
- 相続税の特例を使うには、「誰が相続するか」が重要
- 何よりも、事前の準備・家族の話し合いが最大の対策
話し合いがなかなかまとまらないから。
相続期限までもう日がないので、一旦共有名義にして再度考えよう。
このような安易な考えで共有名義にしてしまうと、後々大変なことに発展していきます。
考えるのを後回しにしていいことなんて基本ないですからね。
家族同士でお金のことで揉めたくない、その気持ちはよく分かります。
でも、揉めるために話し合いをするのではありません。
揉めないために話し合いをするのです。
そのためには、専門家と一緒に冷静に、公平に、しかも被相続人さんの意志もしっかりと反映した形で、一つ一つ整理していきましょう。
不安があるなら、一度プロと一緒に相続の“分け方”と“持ち方”を整理してみませんか?
RE/MAX L-Styleでは、定期的に相続の勉強会を開催しています。

また、9月から定期的に相続セミナーも開催する予定です。
開催日、開催場所が確定しましたら、またこのBlogでお知らせいたしますので、そちらにもぜひご参加ください。
それではみなさまとリアルでお会いする機会も楽しみにしております!