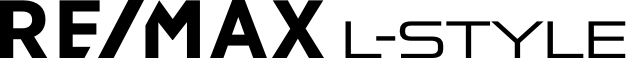その老後、本当に安心ですか?──90歳まで生きるあなたへ贈る“4つの備え”
私たちは今、かつてない“長寿社会”の真っ只中にいます。
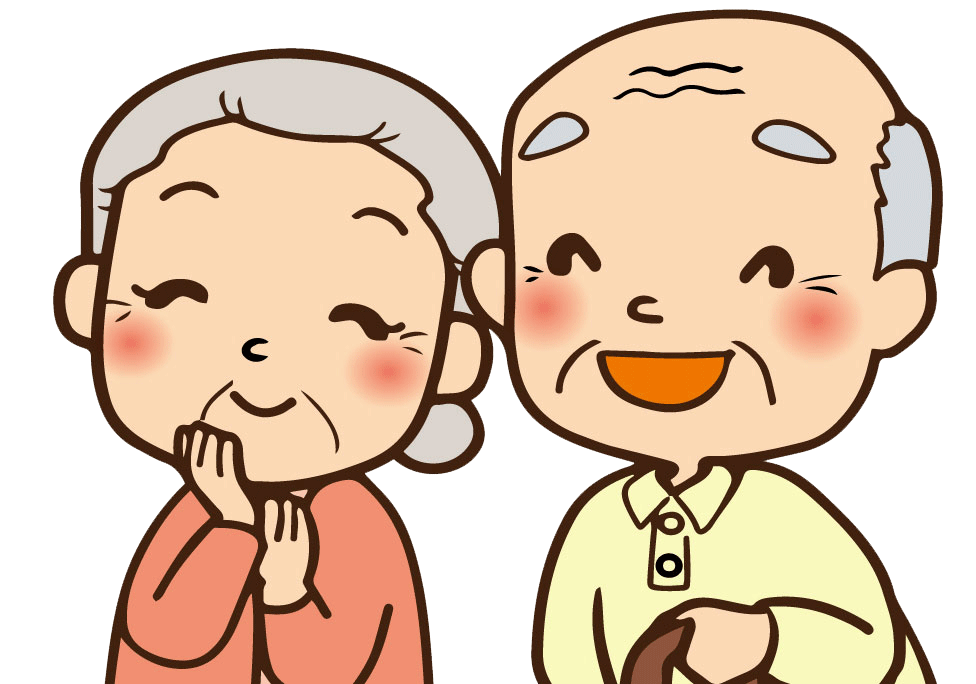
人生100年時代と言われて久しい中で、
老後を「終わりの準備」ではなく、
「新しい人生のフェーズ」と捉える必要が出てきました。
60歳で定年を迎えても、その後に待っているのは
20年、30年という“第2の人生”。
だからこそ、
✔ どこに住み、
✔ 誰と関わり、
✔ どうお金を使い、
✔ どんな想いを遺すのか──
これらを早めに、自分の意志で考えることが、
“幸せな長寿”への第一歩だと、私たちは考えています。
目次
平均寿命の推移
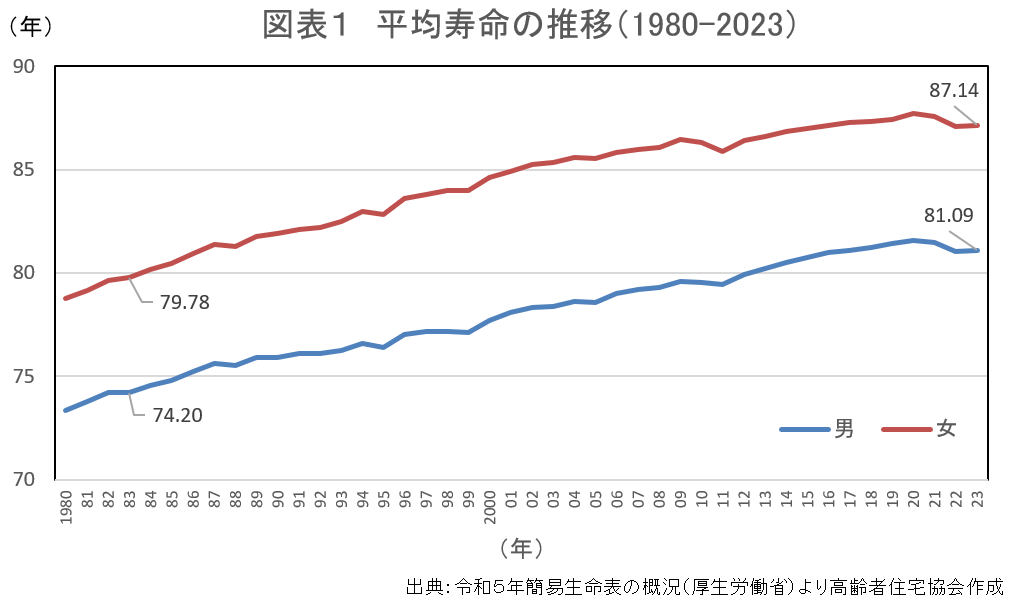
2023年の男性の平均寿命は81.09年、女性の平均寿命は87.14年となり、前年と比較して男性0.04年、女性0.05年延びています。
また、平均寿命を40年前(1983年)と比較すると、男性6.89年、女性7.36年延びました。
この“余白”の6年〜7年をどう捉えるか。
単なるラッキーな延長戦と思うか、
準備不足のまま迎える“アンラッキーな余生”にしてしまうか。
これは、わたしたち一人ひとりにとってとても大切な問いです。
実際に、90歳まで生きる人は今や珍しくありません。
男性の4人に1人、女性の2人に1人が90歳を超えて生きる時代に突入しています。
90歳まで生存する人の割合は男性26.0%、女性50.1%
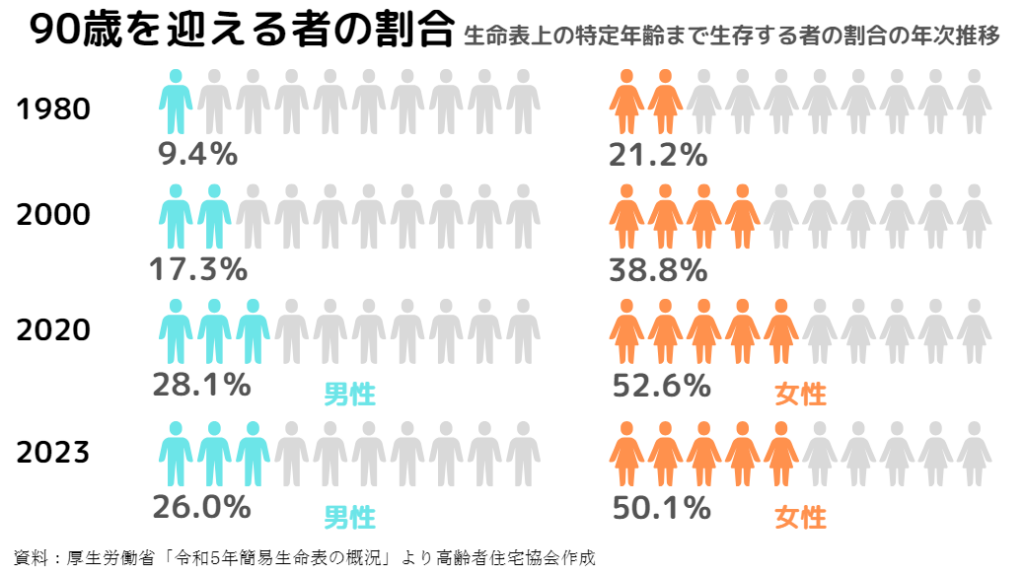
このデータを見て、まずどう感じたでしょうか?
今や、男性で4に1人、女性では2人に1人が90歳以上まで長生きするというデータがあります。
定年退職の年齢が60歳から65歳まで引き上げられましたが、この高齢化、長寿化が原因の一つになっているのかもしれません。
65歳で定年を迎えたあと、
90歳までの25年間を「年金だけ」で生きる時代は、すでに終わりを迎えつつあります。
物価は上昇し、
医療費や介護費の自己負担も年々増え、
親の介護と自分の老後が重なる“ダブルケア”も増えている現実。
この25年は、「悠々自適な老後」ではなく「人生の経営期」と言えるかもしれません。
💡 だからこそ「住まい・お金・関係性」の見直しが必要です
90歳を“特別な年齢”と見るのではなく、
「当たり前に来る未来」として捉えることが、今の時代の“終活”です。
- 今の住まいは、25年後まで安心して暮らせる設計になっていますか?
- 年金と資産、足りると思っていても、計画は具体的に立てていますか?
- もしひとりになったとき、誰がそばにいてくれますか?
これらの問いを、今から少しずつ解消していくこと。
それが「長生きしてよかった」と思える未来につながります。
📚 これから4回にわたってお届けする“終活アップデートシリーズ”
📍【第1章】住まい編|「その家に、あと25年住み続けられますか?」
- バリアフリー、メンテナンス費、立地、階段、孤独…
- 持ち家か賃貸か?二地域居住やリースバックという選択肢
- 住み替えで生まれる“ゆとり”と“安心”
90歳を迎えるまでの“最後の住まい”はどこになる?
リフォーム?住み替え?それとも…?
📍【第2章】お金編|「年金だけでは足りない?老後資金のリアル」
- 老後25年=“3,000万円問題”をどう乗り越えるか
- 不動産を資産としてどう活かす?
- 医療・介護・葬儀…“最後の支出”に備える方法
3,000万円問題は“誰かの話”ではありません。
25年間を安心して生き抜くために必要な資金戦略とは?
📍【第3章】人との関係編|「“もしも”のとき、誰に頼れますか?」
- 高齢単身・老老介護・8050問題…孤立リスクを防ぐ
- 家族会議・見守り・身元保証人という支援の仕組み
- 信頼できる“関係性”をどう築いておくか
家族・友人・ご近所…
孤独と向き合わないために、今つくる“つながりの仕組み”
📍【第4章】デジタル遺産編|「スマホの中の“あなたの人生”、残せますか?」
- 写真・動画・SNS・メール…消えてしまう思い出
- 暗号資産・ネット証券・IDとパスワードの行方
- エンディングノートではもう間に合わない時代に、必要な整理とは?
写真、動画、SNS、暗号資産──
デジタル時代における“思い出”と“資産”の正しい残し方とは?
✨ 次回予告
次回は【第1章|住まい編】
「その家に、あと25年住み続けられますか?」をお届けします!
✔ 老後の住まい選び
✔ 二地域居住やリースバックという選択肢
✔ “売らずに住む”を支える新しい仕組み
あなたと家族の「住まいの未来」を、一緒に考えていきましょう。