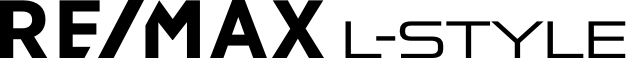「実際に何をする?相続手続きの流れ」初心者でも迷わない完全ガイド【実務編】
相続人の確定、財産内容の把握、そしてリスク回避(相続放棄・限定承認)が終わったら、いよいよ実際の手続きへ進む段階です。
相続手続きって、何から手を付ければいいか分からない…。
そんな不安を抱えるあなたに向けて、この記事では【初心者でも迷わず進められる相続手続きの流れ】を徹底的に解説します。
ここからは、やるべきことが具体的に、そして順番に決まってきます。
今回は、相続発生後に何を・いつまでに・どうやって進めるのかを、
初心者にもわかりやすく徹底的に解説していきます!
目次
【まず最初】戸籍謄本を収集して「相続人の確定」
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を集める
- 相続人全員の戸籍謄本も必要
- 目的:本当に誰が相続人なのかを証明するため
✔ ポイント
→ 不備があると、銀行手続きや不動産登記に進めない!
何を、どこで、どう取る?
- 取るべき戸籍:被相続人の出生から死亡までの全戸籍
- 取り方:
→ 本籍地の役所に請求(郵送も可)
→ 事前に役所HPで請求方法を確認! - 必要なもの:
- 請求者の本人確認書類
- 手数料(1通450円程度)
✔ ポイント → 戸籍が複数市区町村にまたがる場合、どこからどこまでか整理してから一気に請求すると効率的!
🏡【コラム】戸籍は1か所じゃない?本籍が移動するとどうなるのか
「戸籍」と聞くと、「今ある場所だけ取ればいい」と思う方が多いかもしれません。
でも、実は違います。
戸籍は、本籍地ごとに管理されるもの。
そして、人は人生の中で「本籍地」を移すことがよくあります。
🛫 本籍移動は意外と多い!
例えばこんなケース、よくあります。
- 生まれたときは沖縄市が本籍地だったけど…
- 結婚して相手の本籍(大阪市)に変更
- 転勤で横浜市に移動し、本籍も横浜市に変更
- 老後、地元に戻り、再び沖縄市に本籍を戻す
この場合、
沖縄市・大阪市・横浜市、それぞれに戸籍が作られるわけです。
📝 相続手続きでは「出生から死亡まで」の戸籍が必要
相続では、
- 誰が相続人なのかを証明するために、
- 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
が求められます。
つまり、
本籍が移動していれば、そのたびに別の役所に戸籍を取りに行く必要があるということです。
⚡ ありがちな失敗例
「今の本籍地の戸籍だけ取ったから大丈夫!」と思って銀行に行ったら、
➡️ 「出生からの戸籍が揃っていません」
➡️ 「手続きができません」
とストップをかけられる、なんてことも…。
🗺️ どうすればスムーズに集められる?
- まず、現在の本籍地の役所で戸籍謄本を請求
- そこに「改製原戸籍」や「除籍」があるか確認
- さらに、過去の本籍地も役所に問い合わせ、必要な戸籍を請求していく
もし自力でやるのが難しければ、
行政書士さんなどに依頼するのも手です!
✨まとめ
✅ 本籍が移動すると戸籍も増える
✅ 相続では「出生から死亡まで」の戸籍が必須
✅ 1か所で終わるとは限らないので注意!
「相続手続き=戸籍集めから始まる」
この事実を知っているだけで、手続きは格段にスムーズに進められます!
【同時並行で】財産目録を作成する
- プラスの財産(不動産、預金、株式 etc)
- マイナスの財産(借金、未納税金、ローン)
✔ ポイント
→「目録=リスト」でOK。後々の分割協議や税務申告のベースになる!

何をどんな形で作る?
- 推奨:エクセルなどで「財産一覧表」作成
- 項目例:
- 預貯金(銀行名・支店・口座番号・残高)
- 不動産(住所・地番・登記簿記載事項)
- 株式(証券会社・銘柄・株数)
- 借金(金融機関名・契約内容・残債額)
✔ ポイント → 「不動産」は登記簿謄本、「預貯金」は通帳コピーを添付すると後々手続きが楽!
【期限注意!】相続税がかかるかをチェック
- 相続税の基礎控除:
3,000万円+600万円×法定相続人の数 - 基礎控除を超えたら、10ヶ月以内に相続税の申告・納税が必要
✔ ポイント
→ 相続税申告が必要かどうか、早めに専門家(税理士)に確認!
相続税の簡単シミュレーション【実務テクニック】
ざっくり計算例
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の数
- 例)配偶者+子2人=基礎控除4,200万円
試算のコツ
- 不動産は「固定資産税評価額」で見る
- 預金・株式は「死亡時の残高・時価」で見る
【重要】遺産分割協議を行う
- 相続人全員で話し合い、誰が何を相続するか決める
- まとめたら遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印
✔ ポイント
→ 1人でも協議に同意しないと、分割できない。早めに合意形成を!
【ここから名義変更スタート】不動産登記・金融資産の名義変更
(1)不動産相続登記
- 相続登記は義務化(2024年4月〜)
→ 相続を知った日から3年以内に登記申請が必要 - 必要書類:
- 遺産分割協議書
- 戸籍謄本
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
✔ ポイント
→ 登記をしないと、将来売却・譲渡ができない!
不動産相続登記
申請時の注意点
- 法務局に登記申請書を提出(郵送でも可)
- 必要添付書類が多いので、事前にリストアップ必須
✔ よくあるミス → 固定資産評価証明書を取り忘れて再提出になる!

(2)銀行口座の解約・名義変更
- 銀行に「相続手続き依頼」を提出
- 口座凍結解除後、相続人で分配・または名義変更
✔ ポイント
→ 銀行ごとに手続きが違うので、事前に問い合わせしておくとスムーズ!
銀行口座の凍結解除手続き
実際の流れ
- 銀行に連絡 → 相続手続き案内書受領
- 必要書類提出(戸籍謄本・遺産分割協議書など)
- 凍結解除 or 名義変更 or 払い戻し手続き
✔ ポイント → 事前に電話確認し、必要書類リストを必ずもらっておく!

(3)株式・投資信託の名義変更
- 証券会社に連絡
- 被相続人名義の資産を相続人に移す手続き
✔ ポイント
→ 価格変動リスクもあるので、早めの手続きがおすすめ!
相続手続きでありがちな失敗例
- 戸籍の不備で銀行手続きNG
→ 出生までの戸籍が揃っていなかった! - 財産目録作成ミスでトラブル
→ 負債を見落としていた! - 相続税申告期限を過ぎて延滞税発生
→ 申告必要か迷っている間に10ヶ月経過! - 相続登記を放置して後悔
→ 時間が経つと、相続人が増えすぎて手続きが困難に…
相続手続きの全体スケジュール例【見える化】
| 時期 | やること |
|---|---|
| 相続発生直後 | 死亡届提出、葬儀手配 |
| ~1ヶ月以内 | 戸籍収集、財産調査開始 |
| ~3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の検討 |
| ~4~6ヶ月以内 | 財産目録完成、遺産分割協議 |
| ~10ヶ月以内 | 相続税申告・納付 |
| ~1年以内 | 不動産相続登記、銀行口座・株式の名義変更 |
【忘れがち】年金・保険金・公共料金などの手続きも忘れずに!
- 年金の受給停止手続き(年金事務所へ)
- 生命保険金の請求(保険会社へ)
- 電気・ガス・水道・インターネットなどの名義変更・解約
✔ ポイント
→ 生活に直結するものも多いので、優先的に対応!
相続の手続きは専門家の力を借りてもOK!
- 司法書士 → 相続登記
- 税理士 → 相続税申告
- 弁護士 → 相続トラブル対応
✔ ポイント
→ 無理せず、必要に応じて専門家に任せるとスムーズ!
✨まとめ
✅ 戸籍謄本の収集→財産目録の作成→相続税確認→遺産分割協議→名義変更、が基本の流れ
✅ 相続税申告は10ヶ月以内、不動産登記は3年以内
✅ わからないことは専門家と早めに連携!
🔥 最後に
相続手続きは「難しい」「面倒」と思われがちですが、
順番に、そして一つひとつ確実に進めていけば、必ず乗り越えられます。
この記事を読んでくれたみんなが、
不安なく、スムーズに相続を乗り切れることを願っています!